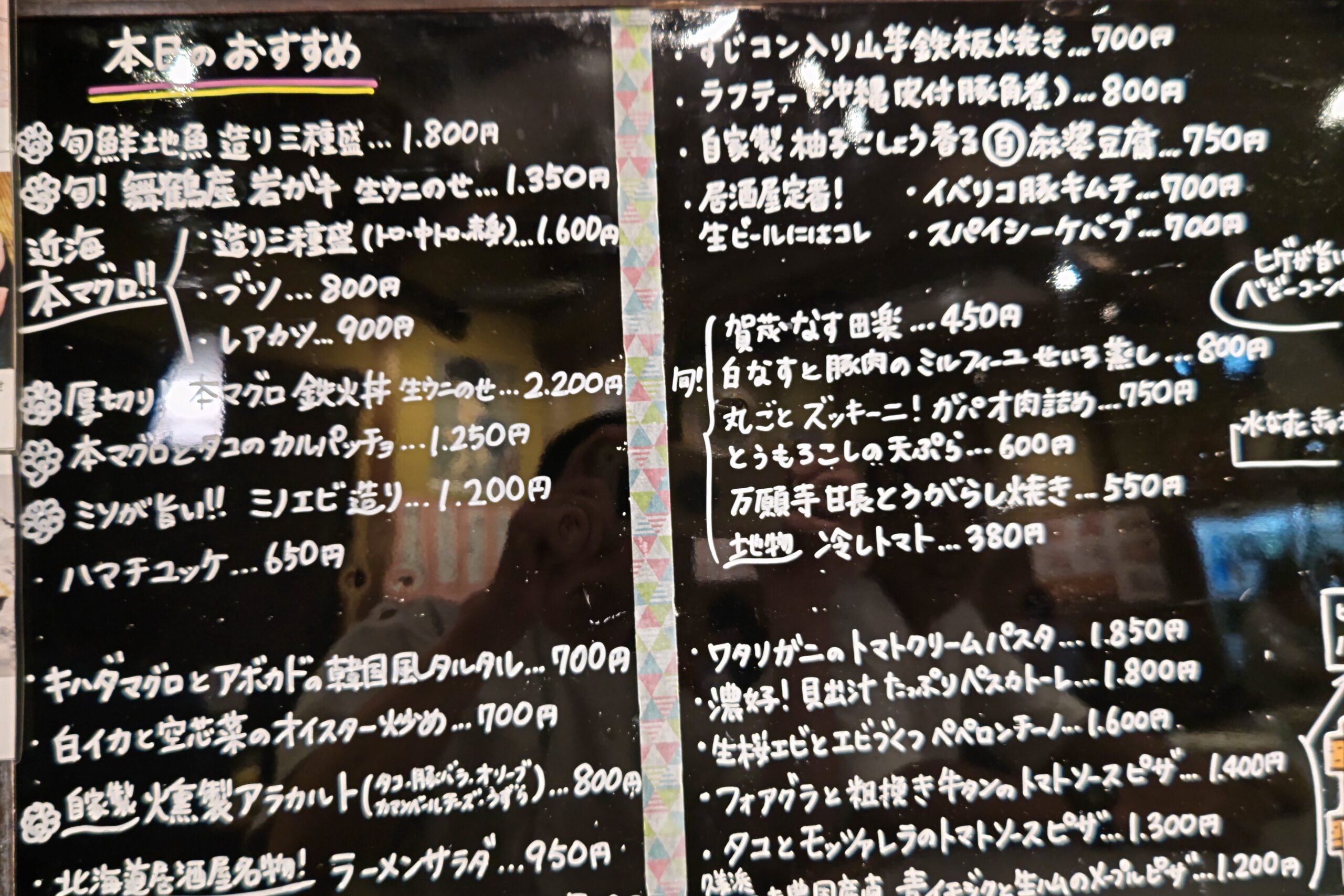夏の夜、ひと粒の岩ガキに心を奪われた
カウンターに腰をおろすと、呼吸がすっと深くなった。
冷たい大理石の感触。
グラスの下にできた水の輪が、まるで「おつかれさま」とささやいているみたいだった。
背後からは気怠げなジャズ。
音が空気にそのまま溶けて、疲れたからだがじんわりとほぐれていく。
仕事帰りのささやかなごほうび。
そんな思いを胸に、ひと皿を待っていた。
やがて目の前に届いたのは、大ぶりの貝殻に鎮座した岩ガキ。
そのうえに、濃いオレンジ色のウニがふわり。
小さなレモンのスライスが寄り添い、氷のうえで涼しく光っていた。

ひと口。
ひんやりとした感触に、背筋がすっと伸びる。
潮の香りと、ミルクのようにまろやかな甘み。
そこにウニのとろける旨みが重なり、思わず目を閉じた。
もし「海の記憶」というものがあるなら、
きっとこんな味なんだろう。
そのひと口だけで、
「今日をちゃんと生きていた」と思えた。
次に並んだのは、ガラス皿に盛られたカルパッチョ。
マグロはルビーのように赤く、
タコは白と紫のマーブル。
レモン、ピンクペッパー、刻んだハーブ。
小さな絵画のように彩られた皿だった。

フォークでそっとすくって口へ。
マグロは絹のようにしなやかにとろけ、
タコはほどよい歯ごたえと冷たさで、
海の奥の静けさを思わせた。
ただ「おいしい」だけではない。
海から来た素材と、料理人の手。
その出会いが、この皿のなかに小さな物語を生んでいた。
耳の奥で、ふと波音がした気がした。
けれどそれはスピーカーからの音楽。
それでも確かに、私は潮風のなかにいた。
そんな夜だった。